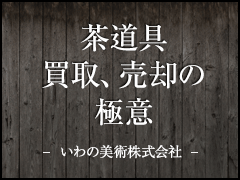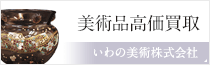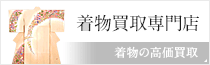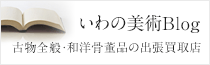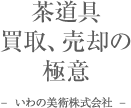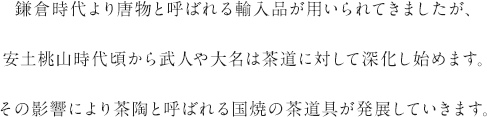
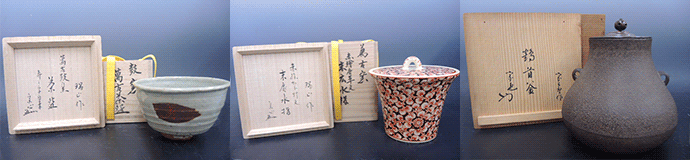
国焼の茶道具が発展を遂げる安土桃山時代に
茶陶・陶芸の名工と言われる人物達が台頭し始めます。
有田郷に陶業がはじめられたのもこの頃とされています。
最初の茶陶の栄えた時と言ってよいでしょう。
明治維新後の日本は欧米の知識や技術を導入していく中で、陶芸の世界でも変化が現れます。
以前の職業的陶工からより芸術性を持つ陶工へ変容します。
それと当時に安土桃山時代の陶芸を復活させるという流れもあり、
明治初期から名工と言われる陶芸家が名声を上げていきます。
その中でも特に著名な人物達をご紹介しております。

昭和を代表する美濃焼の陶芸家で、「荒川志野」と呼ばれる独自の境地を確立しました。
25歳の頃上絵磁器の事業をおこしますが、1922年には失敗して心機一転絵描きを志します。縁のあった宮永東山を頼り手紙を出すと京都に呼ばれ、東山窯の工場長を任されます。
その後東山窯に訪れた北大路魯山人と親交を深め、料亭「星岡茶寮」で使う食器造りを手伝うため鎌倉の星岡窯へ行きます。
1930年名古屋の関戸家所蔵の鼠志野香炉と志野筍絵茶碗を見せてもらったのがきっかけで、現在の可児市久々利大萱で桃山時代の志野、瀬戸黒、黄瀬戸を焼いた古窯趾を発見します。
その後星岡窯を辞め、多治見の大萱古窯趾近くに窯を作り、作陶を始めました。
荒川豊蔵は古窯趾から発見した陶片を頼りに、桃山時代の志野、瀬戸黒、黄瀬戸の復興に力を尽くします。

佐賀県有田生まれの陶芸家で、本名は久重といいます。
上京し、東京多摩美術大学日本画科を卒業すると、神奈川県の法政大学第二高等学校の美術教師として勤務しましたが、その後父に呼び戻され、祖父の興した会社に入社しました。
青木家では代々窯元として業を為してきましたが、1899年祖父甚一郎によって貿易を主とした内外向け陶磁器製造販売を手掛け発展します。
父の代では有田陶業と改名しますが後に倒産し、青木龍山はフリーの陶磁器デザイナーとして生計を立てました。
1954年日展にて初入選を果たし、以降は順調に入選を重ね、会員にも推挙されました。
また現代工芸展にも出品を行い、特別会員賞などの賞を受けました。
当初は地元有田焼の染付や染錦の作品を制作していましたが、後に黒釉を基調とした天目作品を制作し、黒天目や油滴天目をはじめ、金彩や銀彩天目といった独創性ある作品を展開していきます。天目釉による多彩な制作に挑戦し、常に新しい作風を取り込んだ功績から、佐賀県で初めての文化勲章受章者となりました。

本名は板谷嘉七といい、号は初め「波山」ではなく「勤川」としていました。
波山は東京美術学校彫刻科を卒業後、金沢の石川県工業高校に彫刻科の教諭として採用されます。教諭採用をきっかけに陶芸の指導も担当することになった波山は本格的に作陶に打ち込み始め、1899年頃最初の号である「勤川」を名乗り始めました。
1903年教諭を辞した彼は上京し、田端(現東京都北豊島郡滝野川村)に窯場小屋を築き作陶に励みます。
1906年頃号を「勤川」から以降終生使用することとなる「波山」に改めます。
波山は日本美術協会展での受賞を受け、1917年には「珍果花文花瓶」が同展最高の賞である1等賞金牌を受賞しました。
その後1929年に帝国美術院会員、1934年帝室技芸員となり、1953年には陶芸家として初めて文化勲章を受賞します。
また重要無形文化財保持者の候補にもなりましたが、波山は辞退しました。
1963年長きにわたって助手を務めていた轆轤師の現田市松が亡くなると、波山も春に病を患い逝去しました。

伊東善輔の長男として生まれ、12歳の頃円山派の画家であった小泉東岳に日本画を学びます。
その頃東岳が生計を立てるために画業と並行して行っていた茶碗の絵付けや、土瓶造りの手伝いをきっかけに陶業への転向を決意しました。
その後陶工の亀屋旭亭に弟子入りして本格的な作陶を開始します。また3代高橋道八、幹山伝七、岩倉山吉兵衛等の窯を訪問し、研究に努めました。
1867年に京都白河畔に「陶山」を開窯し、茶器や酒器をはじめ創作性の高い作品を制作し、明治に入ると洋食器や装飾品の制作も行い、積極的に海外貿易にも着手します。
その後1909年に工場と店舗を三条白川へ移し、国内外に陶山焼の名を示して隆盛を極めました。
1912年には多年にわたる功績と制作技術を称えられて、久邇宮邦彦王より「陶翁」の号を拝受します。
伊東陶山は墨画濃淡焼付法を発明し、同時に藍染付技法を会得するなど、それまでの粟田焼の作風を覆し、新たな可能性を見出しました。

12代今右衛門の長男として生まれ、東京美術学校卒業後は帰郷して、父親の薫陶を受けて作陶を開始しました。
その後1975年の父親の逝去に伴って、13代今右衛門を襲名します。
若い頃から色鍋島に意欲的で、現代の角度からの色鍋島の制作に取り組みました。伝統を守りながらも常に新しい技法に挑戦し、現代的な作陶を志し、研鑽に努めました。
作品では伝統の色鍋島に、呉須釉薬を吹き付ける吹墨を基本に薄墨、吹重ね等の技法を取り入れた作風を築きます。
日本国外でも高い評価を受け、1989年には重要無形文化財「色絵磁器」の保持者に認定されています。

岐阜県多治見で5代加藤幸兵衛の長男として生まれました。
父5代加藤幸兵衛に師事し陶芸を学びましたが、戦時中の召集により広島で被爆してしまいます。
その後白血病による10年もの闘病生活を経て、作陶を再開し日展にて初入選を果たします。
1961年にはフィンランド政府より招待され、フィンランド工芸美術学校に留学し、その在学中にイラン等の中東地区の旅行も行いました。
中東地区では古代ペルシャ陶器の斬新な色彩や、独創的な造形に惹かれ、以降ペルシャ釉の研究に没頭します。
帰国後も日本で作陶を続ける傍ら、度々イランの遺跡発掘調査などに参加してペルシャ釉の研究を続け、長年にわたる試作の結果、17世紀以降途絶えていたペルシャ釉の一種であるラスター彩の再現に成功しました。
ラスター彩(Lusterware)は気品の高い焼物で、色彩も文様も変化に富んでおり、光の角度によって焼物の表面が虹のように輝く落ち着いた光沢を持っています。
このラスター彩作品は高く評価され、1995年には「三彩」で重要無形文化財保持者となりました。

愛知県瀬戸市生まれの陶芸家で、本名は一(はじめ)といいます。
元々は画家を志しており、陶芸図案化の日野厚に師事していましたが、1926年には岐阜県陶磁器試験場に技師として勤務し、その傍らで作陶を開始しました。
作品は帝展工芸部門で出品と入選を重ね、1930年頃より号の「土師萌」を使い始めます。
1937年にはパリ万博でグランプリを受賞し、1940年に横浜に築窯して独立を果たしました。
東洋の陶磁器に対して高い見識を持っており、中国明代の金襴手で、特に黄地紅彩の技法を解明します。
富本憲吉と共に色絵磁器における双璧と言われ、1961年には「色絵磁器」で重要無形文化財保持者となりました。

本名は金重勇といい、父から薫陶を受けて陶技を磨きました。
若い頃から茶陶の研究に没頭し、桃山風備前の再現に成功しています。
江戸時代中期以降、伊万里焼や九谷焼などに押されて人気の落ちていた備前焼を再興させることに成功し、備前焼中興の祖と称されました。
1956年「備前焼」で重要無形文化財保持者となり、備前焼の陶工としては初めて人間国宝になっています。
自身も優れた陶工でしたが、他に多くの弟子を育て、その中には同じく備前焼で人間国宝となる藤原啓等の優秀な陶工がいます。
また金重陶陽の弟や、息子たちもそれぞれ備前焼で活躍する人気陶芸家となりました。

11代柿右衛門の長男として生まれ、本名は正次といいます。
父親のもとで陶芸を学んでいましたが、1917年父の逝去に伴って12代柿右衛門を襲名しました。
1919年に事業化と共同で柿右衛門合資会社を設立し、赤絵技術と「角福」印を給与しましたが、美術品の制作を志向する12代柿右衛門は会社の経営方針が合わず1928年に関係を解消しています。
以降「角福」銘は使わず「柿右衛門」銘で作品を制作し、1969年に会社とは和解を果たしました。
1953年には初代柿右衛門300年祭を記念して、長男の渋雄(後の13代柿右衛門)と、孫の正(後の14代柿右衛門)と共に、乳白色の濁手素地の技法を再現させています。

京都市東山区五条生まれで、立命館商業学校を中退して石黒宗磨(むねまろ)に師事し、中国陶芸を学びました。
自宅陶房を中心に陶芸活動に専念し、1951年日展にて初入選を果たします。
また1955年に新発足した日本工芸会主宰の日本伝統工芸展に出品し、1960年には同展にて日本工芸会総裁賞を受賞しました。
当初自宅の陶房にて柿釉や青磁、天目や白釉等の作品制作を行っていましたが、1970年に滋賀県蓬莱町に新しく開窯します。
その開窯以来、白釉と黒釉(鉄釉)が造形的に交錯する蓬莱釉作品を創始し、重厚な作域を示して高い評価を得ました。

美濃焼の産地である、岐阜県土岐市出身で父親鈴木通雄も釉薬の研究を行っていました。
岐阜県立多治見工業高等学校窯業科を卒業後、父の勤める丸幸陶苑へ入社しました。
研究者として知られた父から陶土や釉薬について学び、基礎的な知識を身につけた後、荒川豊蔵や加藤土師萌等に師事し、志野焼の研究に励み、技法を体得しました。
作品では1959年に初出品した現代日本陶芸展、日本伝統工芸展で入選を果たし、その後も数多くの受賞を重ねました。
若い頃から志野焼の技法を追求し、独自の焼成方法を考案するなどのことから、1994年に重要無形文化財「志野」の保持者に認定されています。

1895-1985
本名は重雄といい、11代中里太郎右衛門の次男として生まれました。
長男が別の道に進んだため、父親11代の没後に12代中里太郎右衛門を襲名します。
12代襲名後は藩政の時代から使われてきた御茶碗窯を再建し、新しく倒焔式石炭窯を築きました。
また古唐津窯跡の発掘調査を開始し、古唐津の研究と復興に尽力して、叩き作り等伝統的な古唐津の技法を完成させました。
1969年京都大徳寺で得度し、号「無庵」を拝領すると、長男忠夫に家督を譲り、自身は隠居し独自の作陶に没頭します。
その後1976年に重要無形文化財「唐津焼」保持者に認定されました。

東京都青梅市で生まれ、1941年東京美術学校工芸科図案部を卒業後、文部省工芸技術講習所に入所します。ここで加藤土師萌に陶磁器制作の技法を学び、1938年には富本憲吉に師事し、九谷焼系の色絵磁器の技法を習得しました。
戦後、富本憲吉を中心に結成された新匠美術工芸会に加わり、色絵磁器を制作発表します。
その後1955年頃には前衛的な造形作品を制作しましたが、再び赤絵陶器の仕事を手掛けるようになります。1968年頃からは本格的に色絵磁器の制作に取り組み、東京に窯を築きました。
作品は伝統的な作調から複雑な色彩効果を追求し、より写実的な描画法へと発展していきます。それに伴って、地となる白磁釉も青みを帯びて透明度の高い草白釉と、白く半マット状の雪白釉を工夫し、色絵の表現を一層豊かにしました。
1983年頃から地釉の上に本窯の色釉で文様を描き、その上に従来の上絵付けを併用する、釉描加彩の技法を開発し、1986年には色絵磁器で人間国宝となりました。

明治時代を代表する日本の陶芸家です。
陶工の宮川長造(楽長造)の四男として、京都の真葛ヶ原で生まれました。
19歳の頃、兄長平と父長造を相次いで亡くし、兄の家族を引き取って家督を襲名しています。双林寺の画僧であった大雅堂義亮に絵画を習い、1868年には父の後を継いで、虫明窯の陶技指導に岡山へ赴いています。
父親の得意としていた色絵陶器や磁器等を制作し、幕府から献納品の依頼もされていました。
1871年には輸出用陶磁器の製造を目的に横浜で眞葛焼を開窯します。
この真葛焼は薩摩焼を研究し制作されましたが、金を多量に使用する薩摩焼の技法に変わり、精密な彫刻を彫り込む高浮彫(たかうきぼり)という新しい技法を生み出しました。
香山の細密な高浮彫で作られた真葛焼は万国博覧会に出品されると各国の絶賛を受け、真葛焼と宮川香山の名を世界に知らしめ、世界的芸術家として認識されました。
しかし高浮彫は生産の難しさに加え、精度を上げるほどに時間を要する生産効率の低さが問題となり、香山は作風を一変させます。
海外向けの華やかな作品の他にも、茶陶や盆栽鉢でも数多くの秀作が残されており、製作範囲は広かったようです。

出身は山口県萩市で三輪雪堂(9代休雪)の三男として、代々萩焼を家業とする家に生まれました。三輪壽雪は兄の休和(10代休雪)について伝統技法を修行します。
1941年三重県津市に工房を持っていた川喜田半泥子に師事し、茶陶の製作技法を学んでいます。
1955年頃より雅号を「休」と称し、作家活動を始めました。この頃日本伝統工芸展等に出品し、10代休雪と並んで高く評価され、注目されています。
作風は萩焼の伝統を受け継ぎながら、個性的な造形感覚によって茶陶の世界に新風をもたらすものでした。
釉薬は長石釉を用いた萩の伝統的な枇杷色調のものと、10代休雪と共に研究し完成した「休雪白」と呼ばれる純白の藁灰釉を用いたものがありますが、特に休雪白の用法は大胆で斬新な造形と相俟って大きな特色となっています。
1967年兄の10代休雪の隠居に伴い、三輪窯を受け継ぎ11代休雪を襲名しました。
その後も作陶を続け、荒目の素地による鬼萩手などにも挑戦し、独自の成果を見せています。全ての作陶過程を自らの手で行うことにこだわりを持ち、晩年まで活動を続け、2012年老衰のため逝去されました。

本名は北大路房次郎といい、日本の芸術家として晩年まで陶芸家、篆刻家、画家、書道家、料理家、美食家など様々な顔を持ちました。
現在の京都市北区、上賀茂神社の社家の家に生まれますが生活は貧しく、竹屋町の木版師福田武造の養子となり、京都烏丸二条の千坂和薬屋に丁稚奉公に出されています。書家になることを志して上京し、1905年町書家の岡本可亭の内弟子となり、その後1908年より中国北部を旅行し一時期朝鮮総督府に書記として勤めました。帰国後は福田家の家督を長男に譲り、自身は本姓である北大路姓を使い、魯山人と号すようになります。1919年には大雅堂芸術店を開業、また食の造形を深め1921年に美食倶楽部を開業し、自ら厨房に立って料理を振る舞う一方で、使用する食器も自ら制作しています。1925年には東京に星岡茶寮を開きますが、1936年に星岡茶寮を追い出されてからは専ら陶器制作や絵画制作を中心に活動して数多くの作品を残しました。陶芸作品では自由奔放で形式に囚われない、重厚で大胆な造形を展開して、信楽焼、備前焼、美濃焼などの土物から、赤絵、染付、青磁などの磁器物まで幅広く制作しています。

河井寛次郎は島根県安来町の大工の家に生まれ、東京高等工業学校窯業科を卒業後、京都市陶磁器試験場へ入社し、学校の後輩でもあった濱田庄司とともに一万種以上の釉薬の研究や、中国陶磁の模倣や研究を行いました。1921年創作陶磁展覧会で科学的研究の成果を取り入れた技巧華やかな作品を発表して注目を浴びますが、周囲からの評価に反して自身は制作に悩み、一時期作陶を中止しています。その後柳宗悦の民藝運動に深く関わり、1929年古典から日用の器へと路線を変えて個展を開催しました。個展では日本やイギリスの器から受けた影響をもとに実用的で簡素な造形に釉薬の技術を生かした美しい発色の器を発表し、またこれ以降の作陶では日用の器から簡素ながら奔放な造形へと変化していきます。
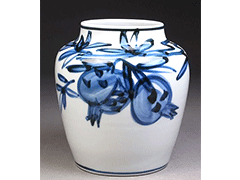
本名は近藤雄三といい、1977年重要無形文化財「染付」の保持者に認定されています。京都市陶磁器試験場付属伝習所轆轤科に入社し、卒業後も助手として暫くは同試験場で勤務しますが、後に陶磁器試験場を辞めて、富本憲吉に助手として師事しました。この時、富本憲吉のもとでは素地や釉薬などの技法だけでなく、制作に対する心構えについても指導を受けています。その後関西美術院洋画研究所でデッサンや洋画の研究をする傍ら、京都市清水新道石段下に窯を作り、染付や釉裏紅、象嵌などの技法を用いた作品を発表しました。1928年の第9回帝展で初入選を果たすと以後13回もの連続入選を続け、他文展などで多くの作品を発表しています。近藤悠三は当初、陶器も磁器も制作していましたが次第に豪放な筆致による染付技法を確立して磁器の制作を専門に行いました。また1960年頃より染付のみではなく、赤絵や金彩などで装飾性を向上させた作品を展開しました。

濱田庄司は神奈川県川崎市に生まれ、東京高等工業学校の窯業科に入学しました。卒業後は同学校の先輩であった河井寛次郎とともに京都市陶芸試験場で主に釉薬の研究を行っています。その後柳宗悦や、富本憲吉、バーナード・リーチとの知遇を得て、1920年にはイギリスに帰国するバーナード・リーチに同行し、1923年にはロンドンで個展の開催も行いました。帰国後しばらくは沖縄の壺屋窯などで学びますが、深い関心を寄せていた栃木県益子町に移住し、柳宗悦や河井寛次郎とともに民藝運動に関わります。作品ではほとんど手轆轤のみを使用するシンプルな造形と、釉薬の流描による大胆な模様を得意とし自由な作陶を行いました。濱田庄司の作品はどれも力強く健康的で、柿釉や赤絵などの技法、独自の文様を施した作品が残されています。

富本憲吉は東京美術学校に入学し、在学中にウィリアム・モリスに影響され、1908年イギリスへ私費留学をしています。日本に帰国後、来日していたバーナード・リーチに出会い、バーナード・リーチが六世尾形乾山に楽焼を学ぶ際に、通訳として同行したことをきっかけに自身も陶芸の道に入りました。富本憲吉は独学で多くの技術を身につけ、陶磁器研究のために信楽や瀬戸など各地の窯場や朝鮮半島にも足を運んでいます。1915年故郷である奈良に本格的な窯を築き、李朝に影響された物や民芸調の作品を制作する中で白磁の焼成に成功しました。その後奈良から世田谷へと住まいを移し、白磁や染付の作品を主流とし、色絵磁器の制作にも励んでいます。終戦後は家族とも別れて京都へ移り、この頃より色絵に加えて金銀を同時に焼き付ける金銀彩の技法を完成させ、格調高い作風を確立させています。造形においても自由な表現の作品を発表し、1955年「色絵磁器」で重要無形文化財保持者となりました。

「半泥子」というのは号で、本名は川喜田久太夫政令といいます。他には「無茶法師」などの号も持っていました。15代続く豪商の家に生まれて裕福な家庭に育ち、早稲田大学卒業後は家業のみならず、三重県会議員なども務めています。財界人として多くの要職に就いて人望を集める一方で、趣味人としてもよく知られ、陶芸、書、絵画など多岐にわたって才能を示しました。中でも陶芸の趣味に関しては、当初陶工に作らせていたものの納得が行かず、50歳を過ぎた頃より自ら本格的な作陶をするようになります。作品では形式張った造形ではなく、自由な発想で作品を展開し、伊賀、志野、唐津、色絵などあらゆる作品を制作しました。

瀬戸の陶家加納桑治郎の長男として生まれ、幼少期より父の薫陶のほか、南画や漢詩にも秀でて、1914年には父の窯の権利の一部を譲り受けて築窯、作陶を開始しています。加藤唐九郎は轆轤技術に優れ、陶土、釉薬、窯の再興などにより桃山期の志野、織部などを再現しています。また「原色陶器大辞典」のように生涯を通じて、陶器資料作成を行うなど陶芸界に多大な功績を残しました。永仁の壺事件という贋作事件により無形文化財の資格を失っていますが、そこまで模写することが出来る程の技量にも注目され、この事件によって一層加藤唐九郎の名は広まりました。

松井康成は大学を卒業後、縁あって茨城県笠間市にある月崇寺の住職を継ぎました。中国や日本の古陶磁研究を行い、1960年境内に築窯して作陶を始め、後に田村耕一の指導を受けて、作陶技法を練上手に絞ります。練上手というのは二色以上の陶土を捏ね合わせたり、積み上げたりし、その断面の模様を器表に生かすように器物を成形する技法です。作られたものが縞模様や木理の模様を表すところから、鶉手や木理手、市松手と呼ばれることもあります。松井康成は当初、自然釉や窯変などの作品を試作していたようですが、次第に中国宗時代の陶器に感銘を受けて練上技法を模索し、現代風な多数の釉薬を用いる独創的作品を展開しました。

京都の出身で江戸時代の絵師、京焼の陶工でもあります。
篆刻家、儒学者として知られる高芙蓉に書を学び、若くして頭角を現していました。
青木木米は29歳の頃、文人の木村兼霞堂を訪ねた際に、書庫で清の朱笠亭が著した「陶説」を読んで感銘を受けて作陶を志します。
陶芸では奥田頴川に入門し、30歳を境に京都の粟田口に窯を開きました。その後評判を得ると、5年後には加賀藩前田家の招聘を受け、加賀九谷焼の再生にも尽力しています。
白磁や赤絵、染付など作域は幅広く、作品は急須を中心に煎茶器を中心に制作しています。
青木木米は窯の中から発せられる、火の燃えるパチパチという音で温度を判断していたため、耳はいつも赤く腫れ上がっていました。
耳が腫れ上がってもその手法を変えることはせず、完治する間もないほど作陶を続けた青木木米は晩年には聴覚の機能を失います。
それ以降、彼は木米ではなく聾米(ろうべい)と号するようになりました。
また陶芸以外にも画や漢学に優れ、頼山陽や田能村竹田をはじめ多くの文人とも親交を深めています。

大樋長左衛門は大樋焼を創始した江戸時代の陶工です。
元は河内国土師に住んでいましたが、1656年頃京都に出て楽家4代目の楽一入に陶芸を学んでいました。
その後加賀藩5代目前田綱紀の命で招かれた裏千家4代家元仙叟宗室に同道し、加賀藩前田家に仕えます。
仙叟宗室が帰京する際、金沢に残り、藩主の前田綱紀から金沢東郊の大樋村に住居を賜り、その地名から大樋姓を名乗ることを許されました。
金沢に留まった大樋長左衛門は飴釉を主体とした重厚で独特な作風を展開していきました。
大樋焼では初代の頃より飴釉を基本に焼かせています。
これは加賀藩前田家が京の楽家と千家との間柄を考慮して黒楽や赤楽の物は極力控えさせ、異なる作風を求めた為とされています。

尾形乾山は江戸時代の陶工で、絵師でもありました。
京都の呉服商の三男として生まれた尾形乾山には六歳年上の兄に日本画家の尾形光琳がいます。
内省的で書物を好んだ尾形乾山は仁和寺の南に習静堂を構え、参禅や学問に励んでいました。仁和寺の前には野々村仁清が住んでおり、乾山は仁清から本格的に陶芸を学んでいます。
37歳のとき鳴滝に窯を開き、その場所が都の北西(乾)の方角にあたることから「乾山」と号しました。
作風には陶芸の師である野々村仁清と、兄尾形光琳の影響を受け、多くの色彩を用いた色絵陶器を制作しています。初期の作品には尾形光琳が絵を描き、尾形乾山が賛を書した合作の作品もあります。
また陶芸のみならず絵画や書にも優れており、江戸に移住した晩年、81歳で没するまで陶器や絵画の制作に手腕を発揮していました。

通称は茂右衛門で、本名は庸徳、京で代々続く質屋で4代目を継ぎました。
元々は清の侵攻から亡命した明人の末裔だったと言われています。
商売より文化活動に向いていた人物で、家業を継いだ後も商売は番頭に任せて、自身は諸芸の恵子に励んでいました。
趣味の一つであった陶芸には特に熱を上げ、36歳の時に息子に後を譲って隠居します。
その後建仁寺に築窯して独自の作陶を始め、京焼最初の磁器焼成に成功しました。
京焼磁器の祖とされ、集まった若手工人達にその技術を惜しげも無く後悔し、京焼の発展に貢献しました。
奥田頴川の門下からは青木木米、高橋道八、尾形周平など輩出しています。
作品は呉須赤絵が最も有名ですが、染付や交趾にも優品を残し、食器などの生活雑器から急須など煎茶道具まで幅広い作品を制作しました。
彼の死後、作品の大半は菩提寺であった建仁寺に奉納されました。
また現存した作品に陶印を捺した物が皆無であることから、陶印は使用していなかったと言われています。

江戸時代の肥前国(佐賀県)有田の陶芸家で、初名は喜三右衛門といいます。
酒井田柿右衛門の名は代々後継者が襲名しており、現在は14代酒井田柿右衛門が当代となっています。
喜三右衛門は乳白色の素地に赤色系の上絵を焼き付ける、柿右衛門様式と呼ばれる磁器の作風を確立しました。作品はヨーロッパにも輸出されマイセン窯や、磁器の発祥地である中国の景徳鎮窯にも影響を与えています。
喜三右衛門の生み出した柿右衛門様式の最大の特徴は、乳白色の素地に余白を十分に残した絵画的な構図です。温かみのある乳白色に、左右非対称の伸びやかな絵模様の優美さは現代の柿右衛門窯の作品にも受け継がれています。

清水六兵衛は摂津国東五百住村(今の大阪府高槻市)の生まれです。
姓は古藤、幼名は栗太郎と言い、幼少時に京に出て、京の陶工だった海老原清兵衛に製陶を学びます。
1771年に独立し、五条坂建仁寺付近に窯を開くと、この頃より六兵衛と名乗り始めました。
その後妙法院宮に出入りするようになり、御庭焼を制作します。
当時の一流文人画家達とも親交が深く、円山応挙や松村呉春に下絵を依頼する等、独自の創意を盛り込んだ合作も残されています。
作品では茶道具を制作することが多く、妙法院宮御庭焼の黒楽茶碗のほか、当時流行していた煎茶器等もよく造っていました。

江戸時代前期の陶工で、生没年は不明ですが17世紀に活躍されました。
生まれは丹波国桑田郡野々村(現在の京都府)で若い頃は粟田口や瀬戸で陶芸の修行をしています。
京焼色絵陶器を完成させた人物と言われ、1644年から1648年頃に仁和寺門前に御室窯を開きました。
「仁清」の名は仁和寺の「仁」と、野々村仁清の通称、清右衛門の「清」の字を一文字取って付けられたと言われています。
轆轤(ろくろ)の技巧に優れ、轆轤の技と華麗な上絵付けで茶壺、水指、茶碗、香炉などの茶道具を多く作り上げました。
野々村仁清は自分の作った作品に窯名だけでなく、自分の落款を用いた初めての陶工と言われています。仁清以前の京焼でも焼物に印を押すことがありましたが、これは製造した窯を区別するためのもので、陶工や作者を識別するものではありませんでした。

刀剣の鑑定や研磨、浄拭を家業とする京都の本阿弥光二の長男として生まれました。
自身も刀剣関係の家業に従事していましたが、その傍らで茶を古田織部に師事し、刀剣の本業の他に茶の湯でも独自の芸術的センスを発揮しました。
本阿弥光悦の作品では楽茶碗や、金をふんだんに用いた金蒔絵といった優雅な作風で、変化に富んだ独特の装飾性を示していきます。
また書では近衛信尹、松花堂昭乗と共に「寛永の三筆」と称され、徳川家光をして「天下の重宝」と言わしめました。
50~60歳代に光悦は能書家として絶頂期に至り、この時期の書には弾力性に富んだ、柔軟でいて秀麗な自信のほとばしる筆致が見られます。

戦国時代から江戸時代初期にかけての武将で、一般には古田織部の名で知られています。
千利休に弟子入りしており、後に千利休が大成させた茶道を継承しつつ、自由な気風を好み、織部好みと呼ばれる流行りを作り上げました。
古田織部は千利休の弟子として、細川忠興等と共に利休七哲に数えられています。
1591年秀吉によって千利休の追放が決まると、千利休と親交のあった諸将が秀吉を憚って現れない中、古田織部と細川忠興のみが利休の見送りに訪れました。
見送りの際、千利休は二人に深く感謝して自作の茶杓を贈ります。
古田織部に贈られた茶杓は白竹で樋が深く通り、有腰で千利休の茶杓の中でも特に薄作りでした。
古田織部はこの茶杓に「泪」と名付け、茶杓用に長方形の窓を開けた筒をつくり、その窓を通してこの茶杓を位牌代わりに拝んだと伝えられています。
その後古田織部は千利休の地位を継承するかのように、天下一の茶人となりました。
武将として織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と三人の天下人に仕え、茶人として千利休に学び、古田重然は武人でありながら茶の湯を追求していきます。
古田織部は千利休の「人と違うことをせよ」という教えを実行し、静謐で自然の作り上げる美を慈しむ千利休と対照的な、自ら作り上げて演出する動的な美を確立させ、流派として育て上げました。
古田織部と関わりの深い茶器に「大井戸茶碗 銘:須弥 別銘:十文字」という茶碗があります。
古田織部は大振りな大井戸茶碗を嗜好に合うよう、一度十文字に割り、一回り小振りにして漆で接着したといいます。既に完成された物に対して、この大胆な行動には驚かされますが、これこそが彼の作り上げた美意識なのだといえます。
また好み物には、ゆがみやいびつさを好んだと言われる沓形茶碗、餓鬼の腹のように大きく膨れた胴の餓鬼腹茶入等が伝えられています。