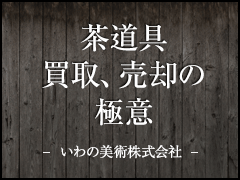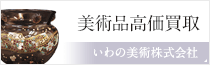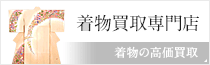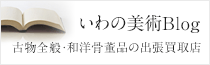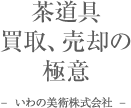玉楮象谷 仙媒 『讃貫彫茶量』 文綺堂黒斎識箱入

****玉楮象谷の仙媒をお買取りいたしました****
白雲が深々と岩を抱くようにたち込める幽谷で、世俗を離れ、本来の自分とひとり向き合う超然とした心境を指す禅語「白雲抱幽石(はくうんゆうせきをいだく)」を冠した漆器仕立ての茶さじです。象谷をうたった贋作が多い中、本作品は象谷の弟にあたる文綺堂藤川黒斎による識箱入りの大変希少なお品をお譲りいただきました。
作者について
玉楮象谷(たまかじ ぞうこく)は1806年生まれ、讃岐国高松出身の漆工職人です。
漆工技術や発展に貢献し、江戸後期にあらわれた讃岐(香川)漆芸の基礎を築きました。
当時の讃岐高松では、素地となる良質の木材が豊富に採れたわけでもなく、漆を産出したとされる記録もありません。しかも乾燥を嫌い、湿潤な風土を好む漆は、雨量が少なく、晴天日数の多い高松の気候にとりわけ適してはいませんでした。では、このような風土にあって象谷はどのようにして特色のある讃岐漆芸を高松の地に開花させたのでしょうか。
象谷は、幼少の頃より篆刻や細字(さいじ)によって名を馳せた父の理右衛門のもとで、家業の鞘塗を習う傍ら、好んで彫刻をなしました。
象谷が漆職人として活躍するようになった江戸後期は、ちょうど工芸技術が発達した時代と重なり、漆工芸においてもあらゆる技法が試みられ、蒔絵に関してはほとんど極限に達した観さえあったと言われます。
このような中で、象谷は父から受け継いだ篆刻の技術をふるい、江戸や京都で主流であった蒔絵にあえてよらず、京都の東本願寺や大徳寺に伝来していた堆朱、堆黒など中国から舶載された唐物漆器や茶人の間で珍重された《キンマ手》とよばれる南方渡来の籃胎(らんたい)漆器に着目し、これらの作品からヒントを得て、地方色豊かな漆器を作り出し、それらを日本的な漆工技法としてよみがえらせていきます。
その理由として、伝統として確立していた蒔絵で門戸を張っていた流派をしのいで新しいジャンルを打ち出すより、自由な発想と発展の余地がある漆芸で、特色のある高松の風土を生かした讃岐漆芸を生み出すことに、より大きな魅力を感じたからだと考えられます。
実際、象谷は、堆黒や堆朱など、彫漆に見られる凹凸のある表面のレリーフ、紅花緑葉の赤と緑の強烈なコントラスト、キンマの線彫りに見られる赤と黒の鮮やかな色彩など、極めてハッキリとした色彩と輪郭線を持つ技法を多く採用しています。自らの屋号を『紅花緑葉堂』と称したことからも、金銀粉を使ったゴージャスさとは異なる配色に魅せられた象谷の性向をうかがい知ることができます。
象谷の独創性による功績は、諸職人が通常、姓を名乗ることのなかった時代において、時の藩主頼怨より『玉楮』の姓を賜り、さらに一種の身分の証でもあった帯刀を許可され、官工しての栄誉が与えられることに繋がりました。
象谷の気風
紀淑雄の『史伝 玉楮象谷』によると、象谷は常にしずかに部屋に座って瞑想し、作ろうとする思いが起こった時でなければ制作のための刀を持たなかったそうです。
また金銭のための制作はしなかったとも伝わり、かつて高松藩のとある武士が金を積み上げて制作を強いたところ、象谷は怒りで顔色を変え、席を立って家に帰ってしまったという逸話も残されています。
常に神を祀り、仏を尊ぶことを怠らなかった象谷は、幼少の頃より備前下津井の木里(きさと)の神を信仰し、生物の命を取る事を絶対的に嫌い、たとえノミや蚊のような虫さえもけっして殺さないどころか残酷な話などを聞くことすらしなかったと伝わっています。
彫刻家の藤川勇造は大伯父にあたる象谷について、「翁の作品にもし鷹がスズメを捕らえているとか、鵜飼その他ヘビなどがカエルを丸呑みするなどの図があったならばそれこそ確実に偽造品である」と触れています。
玉楮象谷作品のお買取りについて
いわの美術では象谷による作品を高値お買取りいたしております。
象谷は、器物を好み、また印刻もたしなんだ上に、京都の永楽焼の門人であった保全のもとで製陶法を学び、楽焼茶碗も少なからず作っています。その多才さと高い名声で知られた作家によるお品は今もなおコレクションアイテムとして根強い人気に支えられています。
ご自宅にご処分にお困りのお品をお持ちでしたら、ぜひ一度弊社にご相談ください。
万が一、お買取り査定額にご納得いただけない場合でも、査定には一切費用はかかりません。
皆様のご連絡をスタッフ一同お待ちしております。